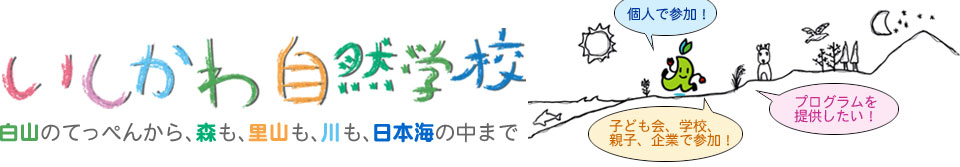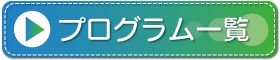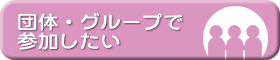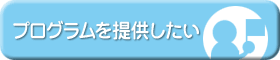カブトムシ博士になろう -幼虫を上手に育てるには?-
開催日:令和7年10月18日(土曜日)13時 30分~15 時 00 分
開催場所:石川県立自然史資料館
参加者:子ども14名 大人8名
カブトムシは、私たちにとって最も身近な昆虫の一つです。一度は成虫や幼虫を飼った経験がある人も多いのではないでしょうか。このイベントでは、カブトムシの基本的な知識や最新の知見を知るとともに、幼虫の適切な飼育方法を学びました。
最初に、バケツの中に入っているカブトムシの幼虫探しを行いました。大きな幼虫はすぐに見つかりましたが、まだ小さい幼虫は腐葉土に紛れてしまい、見つけるのに苦労した参加者もいました。次に、手袋を着けて幼虫にふれ、ルーペを使って体のつくりを観察しました。昆虫に共通する特徴である6本の脚、頭・胸・腹に分かれた構造を理解するとともに、呼吸のための気門の位置や数、土をかみ砕く大アゴ、目が無いなどの幼虫独特の特徴についても学びました。最後に、幼虫のエサになる腐葉土に水を適度に加えて湿らせ、各自持参した飼育容器にしき詰めました。幼虫を飼育する上で水分量は重要で、手で腐葉土を握ると塊になるくらいが目安になります。幼虫の飼育が初めてという参加者は、この加減が難しかったようです。準備ができた容器に幼虫を入れると、すぐに土の中に潜っていきました。残りの時間で、最近の研究で明らかになったカブトムシの「秘密」を学び、みんなカブトムシへの興味が大きくなったようです。
家に飼育容器を持ち帰ったら、腐葉土の表面が乾かないよう霧吹きで水をやり、定期的に腐葉土を交換してあげてください。来年の夏、元気な成虫が出てくると良いですね。